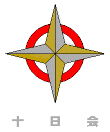事業報告詳細
平成15年度
4月例会「十日会の生い立ち」
今、十日会の役員の方の名前の紹介を聞いていると、名前はわかるが、私の存じている方の丁度孫の世代になっている。その三代目の若い人達が、十日会の運営をしていることを大変嬉しく思い、十日会の歴史を引継ぎ、活発に活動している皆様に感謝している。年をとり、忘れた事も多いので、私の記憶を思いだしながら話をするので、脱線したらご容赦願いたい。詳しくは区切りの年に出版されている記念誌に細かく書かれているので、参考にして頂きたい。当時の事を思い出しながら話をさせて頂く。
十日会の話をするには、高浜二郎先生を除いては語る事が出来ない。高浜二郎先生はずっと和服で過ごし、洋服を着たことがない方で、戦争中に鍍金組合の事務局をおやりになっていて、めっき業界を非常に愛していた方である。戦後は「めっき」という業界雑誌を発行して、その傍ら、めっき業界を焼け野原から復活させようと一生懸命奔走された。業界のために一生を捧げられた方である。
十日会を作っていただいたのがその高浜先生で、「めっき業を善くするには、若い人達に頑張って貰はなくてはならない」との先生の呼びかけで、永年めっき技術の指導を行っている鵜飼義一氏や清水竜一氏、石川清太郎氏、折原義一氏、小宮山正道氏、坂手勇氏、平沢秀恭氏、青木一郎氏と私などが、昭和23年11月15日に後楽園の涵徳亭に集まり、初対面ながら、みんな胸襟を開いて盛んに談論を行い、月に一回会合を開こうという事になり、規約などを決め、会の名前を鵜飼先生の発案で「おしゃかの会」とした。第二回目の会合が12月10日で、毎月十日に集まろうと言う事で、会名を「十日会」と名づけたと記憶している。
それから毎月十日に当時の鍍金組合の平屋建て瓦葺きの事務所に集まり、鵜飼先生を初め田島栄先生、早稲田の吉田忠先生、服部久一郎先生、奨励館の虎石成美先生などを講師としていろいろな事を教わった。話の中で、吉田先生が「ニッケルめっきにサッカリンを入れると艶が出るよ」と言われ、朝まで待てずにその夜に実験したが、サッカリンだけではあまり光沢は出なかった。また、大場鍍金さんに「ニッケルめっきにニカワを入れると艶が出る」という話を聞き、しょうゆ樽にニッケルめっき液をくみ出してニカワを入れたら、これは物凄く光沢が出てピカピカになり、夜も眠れないくらい嬉しかったことを思い出す。しかしニカワだけでは2、3日経つとめっき表面がガラスが割れる様に割れてしまったことを記憶する。
このように外国の文献をもとにめっきの新しい技術を学び、会員同士がお互いに成功談、失敗談を語り、十日会に行けば逸早く新しい知識が伝わると、皆一生懸命勉強した。そして毎月会っているうちにお互いが親しくなり、我々の集う場所を作ろうではないかという事になった。そして会員や員外有志の寄付をもとに、昭和25年6月に湯島の丘に東京鍍金会館を建設した。当時、自動車を持っているところはほとんどなく、寄付を願うため私も自転車に乗って懸け回ったことや、ある長老から「極道息子がとんでも無い事を始めた」などと苦言を言われた事を思い出す。また、東京鍍金組合の幹部の方にも、若い者の別派行動の集まりだということで、あまり善い目では見られなかった。その後、昭和42年に東京都鍍金工業組合のめっきセンター建設の話が現実化した折、「組合の立派な建物が出来るなら、自分たちの会館を売って、その資金を建築費の一部に提供しよう。この事を銅版に刻んで『道標』として後世に残れば良いではないか。」として、試験室の機材と共に組合に寄付した。
ある時高浜先生から、東京だけでなく日本中のめっき業の若手が手を取り合い、情報交換を行い交流を深めようではないかという提案があり、まず大阪鍍金組合の伊藤宗太郎氏や佐藤仙十郎氏達の協力で、大阪のめっき工場を見学した。夜行列車で大阪に着き、モンペ姿の高浜先生を先頭に2、3のめっき工場を見学した後、今里の旅館で大阪の人達と座談会を開き、いろいろな話を夜遅くまでした事を思い出す。これをきっかけに、大阪や名古屋の若手との交流が深まり、東西連合の組織を作ろうという機運が盛り上がり、昭和36年6月、大阪鍍友会、名古屋名鍍会と十日会の三団体で連合会を設立。アメリカのAESに習い、名前を日本鍍金協会にしようということになった。日本鍍金協会では名前負けしないか、日本のめっき業界が困りはしないかなどと考えたが、日本には金属表面技術協会とか全鍍連があったが、日本鍍金協会は無かったので決めてしまった。その後、大阪の鍍生会も参加し、今日まで活発な幅広い活動を展開している。
ここで、国際交流の推進者で、十日会の名誉会員であるエズラ・A・ブラウント氏について語ると、ブラウント氏はアメリカの表面処理専門誌プロダクツ・フィニッシングの主筆で、昭和26年6月に空軍技術中佐として来日、立川空軍整備隊に勤務していた。ある時、都立大の田島栄先生から、ブラウント氏が日本のめっき工場を見学したいと言うので、宮田製作所、日本光学、精巧舎、東平鍍金や会員の工場を次々案内した。これをきっかけに交流が深まり、ブラウント氏からアメリカの新しいめっき技術や設備などの講演を聞き、大変参考になった。約一年後、ご家族の不幸で急遽アメリカに帰国、除隊されたが、その後も交流が続き、昭和34年4月に日本生産性本部が行った第一回アメリカ電気めっき工業視察の時には、見学工場を紹介していただき、その後も日本のいろいろな団体がアメリカを視察する時には大変お世話になった。また、日本鍍金協会の創立25周年記念の折、塚本寛六会長始め協会の人達が資金を出し合い、ブラウント夫妻を日本へ招待。その後も何回も来日されており、日本のめっき業界の発展のために永年に渡って貢献している。今でも90歳を過ぎ高齢となっているが、夫婦ともに元気で、私の家族とは今でも便りをやり取りしている。
十日会が発足した当時は、東京は焼け野原で、めっき工場も粗末なものであったが、ゼロからのスタートであり、一生懸命に仕事をすれば誰でも商売になった時代なので、みんな切磋琢磨する事で各人とも得る物があった。それと、上り坂経済なのでどんどん仕事が拡張していて、お互いが仕事の取り合いなど無く、同業者、グループ同士が助け合って経営できる時代であった。しかし、今は仕事が減少してゆく中で、この十日会の会員の中でも下手をすれば仕事でぶつかる事も考えられる時代である。十日会創立当時はお互い秘密の事を話し合っても、自分の商売に影響する時代ではなかった。今、過ぎ去ってみればやり易かった時代ではないかと思う。現在の方が余程難しい。
企業を存続するには非常に難しい時代であるが、難しければ難しい程世間を広く見なければならない。この時代に、こうして大勢の人が集まり、話し合いの出来る場があるというのは、皆さんが危機感をもとに団結しているのではないかと思う。それも若き力ではないかと思う。現在と当時では状況が違うが、当時も皆で集まる事で得る物が非常に多かった。その後十日会も一時停滞していた時期もあったが、今はかえって私共の当時と同じように皆さんが活発に会合に参加し、幅広く集まっている様子を見て、時代が混沌とした中で、出来るなら同業でも大勢の人と手を携えていたほうが自分も歩き易いと言う事を加味しても、現在皆さんがこれだけの活動を出来ると言うのは皆さんの努力の結果であり、先輩として「ありがとうございます」とお礼を言いたい。ぜひ勉強して、業界の発展のために頑張っていただきたいと思っている。
戦後、兵役から帰ってきて仕事を始めた頃は、ニッケル板も新しい物が無くなかなか手に入らなかった。軍事工場から出てきたアノードのシャブリかすのような物を買い集める事も仕事の一つであった。そんな時、当時上村工業の支店長であった、今日出席の上村さんのお父さんに「いいのがあるよ」とデボライズドアノードを分けて頂いた事を今でも覚えている。比べて今は物があり余っているが、今の時代は本当にやり難い時代だと思う。自分の本業を守り抜く事も大変で、ここにいる皆さんは努力で現在を勝ち取っていると思う。本当に今の日本経済は先が見えない。以前は銀行があのようになるとは想像も出来なかった。やはりアメリカでも15〜20年前に銀行が潰れるという状況があった。日本でも昭和の始めに銀行が潰れるような時代があった。50年に一回か100年に一回、銀行も潰れるような経済変動がある。あってはならないことだが、皆が嫌がる戦争もまた起きてしまった。世の中は繰り返される。その時に発展する物と無くなってしまう物がある。人間生きて行く為には前向きな考え方をしてゆくことが大切だと思う。
現在は不景気ではなく、世の中が変わったと考える必要がある。変わった世の中で生きてゆくことを考えなければならない。私も60歳で社長を譲り、10年ほど仕事から離れて、その後会社に帰って現状を見て、世の中の変化を大きく感じた。私の工場はわれわれの業界では自動化も進んでいた方で、各職場が専門的な仕事になっていた。当時は少し進んだ仕事をしていると仕事が頂け、量が出るから自動化も出来る。例えばゴルフのシャフトを自動化すれば、その仕事だけ行っていれば非常に楽である。しかし、自動化すると決まった物以外はなかなかやり難い。新しい仕事には手を出さなくなってしまい、「福井電化に行っても相談に乗ってもらえない」との声が聞こえ、反省するチャンスを得る事が出来た。新聞に「めっきでお困りの方は何でもご相談ください」と小さな広告を出した。一週間に大手メーカーを含めて30社くらいのいろいろの問い合わせがあった。こんな小さな広告でこんなに反響がある。皆が今困っている。何とかしようと考えた。めっき屋として「めっきでお困りの方は何でもご相談ください」という偉そうな広告をして、自分がそれに答えられる工場にならなくてはと三年間言い続けて来た。
ゴルフシャフトの仕事がゼロになり、そこに小物用のハンドバレルの装置を、穴の大小などいろいろな形のめっきに対応できる様に作った。どんなサンプルも嫌な顔をしないで仕事をしようと頑張り、他でうまく出来なかった物を何とかやろうと努力した。それが出来ると、それに付随する仕事があちこちから言い伝えでやって来た。これは、ほかで出来ない物に前向きに取り組んで「顧客の要望に答えようと努力する」という考え方の蓄積の結果であり、売上も増やす事が出来た。新しい物に挑戦した事で、現在の会社がある。
永年行っている仕事に比べ、アイデアを込めた仕事をすれば手間はかかるが、高い金額の仕事も入ってくる。現在、ニッケルアレルギー対策がヨーロッパで問題になっており、ボタンなどもニッケルを使わないめっきに変わっている。これに挑戦するとニッケルめっきの数倍の単価を頂ける。また、検針対策でもニッケルめっきは磁石に反応するのでそれに変わるめっきが要求されている。それに答えるとやはり高い単価が頂ける。一方、現在は宅配便が発達しているので特色のある仕事をすれば日本中から仕事が来る。そうなったのも時代が変わったからで、いまが不景気だ、不景気だと言うのではなく、前向きに物を考えて対策を立てて手を打てば、まだまだ我々の業界は仕事があるのではないかと思う。また、そういう仕事を生み出す、めっきを付ける事によって、お客さんの販路が拡大できる。お客さんの要望に応えられる工場経営をすれば生き残って行けると思う。
お客さんの方も、従来の製品が毎年減少していて、お客さんも努力して新しい製品で会社を維持している。電子工業関係なども二年も経たないうちに中国へ行ってしまう。量産品は追わない。試作品工場で生き延びられれば、工場は大きくならないが会社の存続になり、次への解決の糸口が開けてくるのが現状だと思う。現在は不況なのではなく、新しい時代に変わったと考えて頂きたい。皆さん、それぞれの立場で実践し、お互い肩を組み手を握り合って、業界のために頑張っていただきたい。
参考:日本表面処理新聞、表面技術ジャーナル
>>戻る
5月例会「新製品紹介」
●2液補給液仕様無電解Ni−Pめっき液
上村工業株式会社
ニムデンNKY
ニムデンNKYは、従来不可能とされていた高濃度(24%)の水酸化ナトリウム単独溶液でのpH調整を可能にした無電解ニッケル−リンめっき液です。水酸化ナトリウム溶液を直接めっき液に添加しても、白濁した水酸化ニッケルが全く発生しません。従って、めっき液の安定性が大幅に改良されたため、驚くほど安定で長期間の使用が出来ます。
つまり、
- 濃縮化で、ランニングコストを最大限に抑えました。
- pH調整に水酸化ナトリウム溶液、及びアンモニア水のどちらでも使用できます。
- めっき皮膜の光沢が優れており、浴の老化による光沢低下がありません。
- P含有率(9±0.5wt%)の変動が少なく、皮膜の物性が非常に安定しています。
- 皮膜の内部応力が小さく、ご要望の「厚付けめっき」が可能です。
- 析出速度が速く(20μm/h at90℃)また、めっき条件の設定で一定した速度維持が可能です。
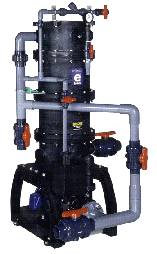
●コスト低減型ろ過機
株式会社三進製作所
逆洗式精密ろ過機 エコエース“Tシリーズ”
エコエースTシリーズは、FD型自動ろ過機をもとに、独自に開発した特殊チューブラータイプTろ材を搭載し、運転コストを大幅に下げると同時に、高精度で安定した精密ろ過を実現します。また、従来のカートリッジ方式等に比べ、廃棄物の質量・廃棄コストも大幅に削減できます。
Tシリーズの特徴は
- 特殊チューブラーTろ材の採用でろ過精度は極めて安定。
- 瞬間逆圧ろ材洗浄方式は操作も簡単で効果抜群・・・10秒で操作完了
- ろ剤寿命が長く運転コストと廃棄コストが大幅に低減。
- ろ過助剤の使用量は約半分・・・自社製品比
- 無助剤ろ過運転も可能・・・但し液種などの確認が必要です。
- ろ材洗浄後のろ滓(逆洗スラリー)はエコエースBシリーズとの組み合わせで簡単に処理できます。
>>戻る
7月例会「めっき難素材の前処理法 〜 新しいめっき技術へのアプローチ」
めっき難素材の前処理法を体系付けて解説する事は難しいが、今回は全鍍連の「新素材へのめっき技術の開発」の報告書をもとに処理プロセスの考え方を中心に話を進めたい。この報告書では、素材や薬品の性質、種類と成分、処理工程、市販の処理法などについて調査結果をもとに詳しく説明しているため、試し実験の手掛かりとして、また、プロセスの考え方を学ぶ上での良い教材でもある。
初めに、めっきがし難い素材の特徴を分類すると、
- 酸やアルカリに侵されやすく、置換反応を起こしやすい。
- 合金系が複雑で、均一な処理がし難い。(亜鉛、アルミ、マグネなど)
- 多孔質や巣などの表面欠陥が多い。(ダイカストや焼結合金など)
- リン、ベリリウム、鉛、ケイ素などの不活性な元素を含んでいる素材。
- 強固な不導体皮膜を形成している、または酸化皮膜を形成しやすい。(チタン、タングステンなど)
- プラスティックス、セラミックなどの不導体。
- 硬い表面
- 細かい、線材、針状、粉末形状など
である。
まず、チタン、モリブデン、タングステンの素材の特徴は、酸化皮膜を形成しやすく、いくら活性化処理をしてもめっき前の水洗工程で酸化膜を作ってしまうことである。つまり、めっき液に入った時には既に酸化膜が生じており、その上にめっきが付くという状態で、密着不良を起こす事が大きな問題である。
たとえばチタンの前処理法としてASTM法というのがあるが、工程の中で表面を粗し密着を良くするために濃いふっ酸と硝酸による化学エッチングを行う方法が記載されている。しかし、この方法は現実に危険で出来ないし、処理の意義や役割を考えて選択する事が重要である。そこで、とりあえず一般的な処理方法で行ってみて、それでダメならストライクめっきを行う。酸性サイドであればニッケル、クロムストライク、アルカリサイドであれば銅や銀ストライクというように素材との相性によって選択すればよい。ストライクめっきは酸化膜を形成しやすい素材には重宝である。
ただし、チタン、タングステンなどの素材は、細い、線材、針状などの形状が多いので更にやりにくい。このような形状への対処法も考えると面白い。ニッケルストライクを嫌う場合には、金、白金、ロジウムなどの貴金属ストライクめっきを活用する事も必要である。これにはめっき液中の金属イオン濃度を低くして、相手方の錯化剤やシアン濃度を高めてめっきの付きを遅くして水素ガスをどんどん出すような形にすればみんなストライク浴になる。このような対応も必要ではないか。その他、水洗時での酸化を防ぐために、活性化後に酒石酸やクエン酸によってチタンと溶解性錯塩を形成させて、直接めっき浴へ入れる方法などがある。
次にプラスティックスのめっきであるが、プラスティックスは金属結合が得られないので、物理結合を得るための表面のエッチングがポイントになる。そのために各樹脂に合ったエッチング法を選択しなければならない。エッチングの状態と密着強度との関係から最適条件を見つけることが重要である。エッチングさえうまくいけば無電解めっき法は確立されているので問題ない。
ポリカーボネートやポリアセタールなどの結晶性ポリマーの場合、クロム酸や硫酸のエッチングではなく、塩酸やリン酸などの酸を利用しうまく凹凸を作る方法があるが、鉄鋼材の酸処理に似ていて面白い。また、プラスティックスめっきの場合には、めっきグレードがあるように、素材側からのアプローチも必要である。
セラミクスへのめっきは、配線基板で非常に熱特性が優れているということで使用されているが、これもプラスティックスめっきと同様にエッチングがポイントになる。形成された表面層にちょっと違った表面層が出来ており、それをうまくエッチングに利用する方法である。パラジウム触媒を付けて無電解めっきに入って行くが、このパラジウムの付与の仕方も重要なポイントになってくる。あまりパラジウム触媒を付け過ぎると、パラジウムの上にパラジウムが付き密着不良を起こす。パラジウム触媒の表面の付着量まで考慮する必要がある。また、エッチングによる凹凸をめっきでうまく埋め込まないと密着強度が高まらない。無電解ニッケルめっきは非常に微細なめっきなので凹凸に入りやすい。それに対して無電解銅は結晶粒が大きいために入りにくいため、セラミクスのめっきには無電解ニッケルが採用され、また、めっきスピードを制御する工夫も行われている。
次にアルミニウム、マグネシウム、亜鉛合金であるが、これらの金属は酸やアルカリに侵されやすく、また、置換反応を起こしやすいのでストライク銅めっきが必要になる。アルミニウムの亜鉛置換法は、水酸化ナトリウムと酸化亜鉛を基本とする置換液で処理する物で、この置換を過激にやると密着不良を起こすので、置換反応を制御する工夫がされている。
また、マグネシウムは合金系が非常に複雑なので、均一な処理をする事が難しい。更にダイカストなので多孔質で巣などの表面欠陥が多くめっきがやりにくい。マグネシウムの前処理は、活性化処理として高濃度のクロム酸を使用し、表面を50μmほど削るような処理方法があるが、これは廃液処理に問題がある。代替処理方法として、錯化剤を使わざるを得ないと思う。マグネシウムのめっきプロセスを考える場合には、アルミや亜鉛のプロセスと比較し参考にすると良い。
それから窒化チタンや炭化チタンなどの硬い表面へのめっきも密着不良を起こしやすくめっきが難しい素材である。なぜかというと、窒化チタンや炭化チタンは金属結合ではなく共有結合なので、結合力が強く硬い皮膜である。この上にめっきを付けても金属結合には振り向いてもくれないために密着強度が得られない。焼結合金も非常にめっきしにくい素材であるが、磁性材料が需要拡大していることから、焼結合金へのめっきも大きく伸びる事が予想される。樹脂による含浸封孔法が一般的であるが、焼結技術の進歩とともに直接無電解めっきも可能になるのではないかと思う。
以上、めっき難素材の前処理法について解説したが、難しい材料が持ち込まれたら、ぜひこの報告書を参考に試してもらいたい。
次に新しいめっき技術へのアプローチとして開発した、ホウ酸の代わりにクエン酸を用いた電気めっき法について説明したい。このめっき法は、ホウ素の排水規制に対応してワット浴のホウ酸を単にクエン酸に置き換える事で、ワット浴とほぼ同様の作業条件での使用が可能な世界初のニッケルめっき技術である。
私は昭和四十六年に入所以来、非シアン亜鉛めっきの研究とか、その時代、時代の業界が抱えている課題をテーマに研究を重ねてきた。新しい研究を行うには、過去に実験した経験の積み重ねが必要で、その体験がなければすぐには対応できない。常日頃から実験を繰り返し行っていることが今回の開発に結びついたのだろうと思う。
また、正確に実験を行うことが重要である。pHの変化、電圧の変化などの結果には必ず根拠がある。それから観察、記録も必要だ。この実験には山本鍍金試験器の2リットルビーカー用実験装置を用いたが、この装置はアノードやエア撹拌などがビーカーにきちんとセットできるので、正確な実験ができた。また、パソコンによる図形ソフトを使って簡単にデータ作成ができた事も成功に結び付いたと思う。
さて、ホウ酸は水素発生反応を抑制するだけであるが、クエン酸は水素発生反応抑制、プラス、キレート作用を持っている事が大きな特性である。ニッケルイオンと錯体を形成したクエン酸を介してニッケルの電析が行われるため、水素発生が抑制され、添加剤なしでも微細で硬い皮膜が得られることから、ホウ酸の代替技術としてのみならず、クエン酸浴の特性を活かした新しい機能利用の可能性が期待できる。
これからめっきで使用する薬品の規制が進むと思うので、前処理などにもクエン酸やリンゴ酸、グルタミン酸といった体に良い物質を利用した健康志向型めっきプロセスの開発を夢見ている。
参考:日本表面処理新聞
>>戻る
11月例会「1000億円を失って知った価値の根源」
ここに「日本の金満家63人」という資料がある。これは1988年、バブルピークの一年前に、「週刊現代」に掲載された記事である。その中に私の項目があるが、この時の私の資産総額が1000億円と出ている。なぜかというとウィークリーマンションを始めて、すでに借入金が1000億円だったが、その当時借金して買った土地、建物の評価額が2000億円とも3000億円とも言われていた。その額から借金1000億円を差し引いた額が、どう少なく見積もっても1000億円は下らない、とランキングされていた。
しかも借金して資産をつくった会社は、株式会社ツカサでもウィークリーマンションツカサでもなく、親から引き継いだ街の不動産会社である、ツカサ建物管理有限会社なのだ。資本金500万円。つまり私の個人会社だ。実質的な個人で興銀、長銀、日債銀、三井、三菱などから100億円以上のお金を借りたのは。多分、私が最初で最後だと思う。有限会社との取引はお宅が初めだ、といつも同じことを言われた。資本金500万円の有限会社でも、100億円以上のお金を借りられる実績をつくったのだ。ただし私を除いた62人は、それぞれ富豪に相応しい生活をしていた。年収は5億、10億円、田園調布何十坪の住まい。私ひとりだけ、年収900万円、当時の住まい借地の28坪。当時から軽自動車しか乗らない。生活そのものは、ごく普通のサラリーマン並の生活をしていたのだが、その当時、大富豪だったのは歴然たる事実だった。
それが、「ある日突然」という言葉があるが、忘れもしない90年の3月27日に、大蔵省の通達が各金融機関に回った途端に、今後一切、不動産屋に金を貸すなとなった。それを境にして、それから数年で借金はピーク時に最高千四百億円を越えた。にもかかわらず、バブル崩壊前は三千億円とも言われていた資産は、10分の1に減った。当時はプラス1000億円だったのに、数年したらマイナス1000億円になってしまった。都合、2000億円を失った。そういう体験をした。
人間は、こういう体験をして初めて目が覚める。誰でも日々真剣に物を考え一所懸命に仕事して、一所懸命に生活していると思っているだろうが、昔から人間が本当に物を考える時は、3つあると言われている。1つ目は、死ぬような病気を体験する。2つ目は、会社を倒産させる(我が社は倒産しなかったが、ヘタな会社の10や100をツブしたのと同じ規模だ)。3つ目は、何かの理由で投獄されるかだ。そういったことを体験しないと、本当には物を考えられないと思う。私は1000億円を失ったお陰で考えられるようになった。
そういう体験をさせられた結果、94年の中頃から時間が取れて、まず経済に関する本を読みあさった。半年で300冊ほどだと思う。これを読んでまずわかったことが、驚いたことにバブル最盛時の86年〜89年の段階で、日本のバブルは崩壊するとか、銀行が三分の一消えるとかというタイトルの本はすでに出ていた。それらの本の中には、その後起きたこと、起きつつあることが全部書いてあった。何でこんな本を前に読んでおなかかったのかと思った。それで分かったのは、世の中には誰もが予測できなかったことが、ある日突然起こるということはまずない、ということ。バブルの崩壊は十分に予測されていたし、十分に警告する人は沢山いた。それを自分が読まなかった。単に知らなかったのである。
半年間で、自分なりに納得できるような経済の流れを勉強し理解すると、だんだん見えてくるものが変わってくる。それは、原因と結果は繋がっているから、今起きていることは過去の結果として起きていると言う事。つまり、これから先何が起きるか、と考えるようになった。では、将来を見るためにはどういうものを勉強したほうがいいか。将来というものは現在起きつつあることの結果として起きるのだから、現在起きつつあることを正確に把握することが大事なわけだ。それで始めたのが(現在も続けているが)、新聞は日経、朝日、読売、産経、日刊現代、夕刊フジの6紙に全部目を通す。それ以外にダイヤモンドや東洋経済、日経ビジネス等、経済誌を中心に、現代、ポスト、文春ら一般誌を含め20数誌に目を通す。それを長期に読んでいくと、ひとつひとつの記事は点でしかないが、時系列的に並べてみると、そこにははっきりと絵が出てくる。先が予測出来るようになるのである。
当然のことながら例えば一週間後の株価がどうなっているかは予測出来ない。しかし、より大きな流れのなかで、この半年間、日本経済でどういうことが起こったのかとか、どこの銀行がおかしくなったのかとかはみんな書いてあるから分かる。さらに中長期的に見て2、3年後にどういうことが起きてもおかしくないかということも分かってきた。その中で、私が予測して話したことが的中したことがいくつもある。これを私が始めたのが94年の中頃だが、最初に当ったのが、94年の12月に東京協和と安全信用の二つの信用組合が破たんした。この時に勉強会の最後に、「次はコスモ信金だよ」と言った。事実コスモ信金は半年後の九五年に破たんした。コスモが破たんした時に、恐らくこの次は関西の木津信金か兵庫銀行だと言った。一か月後に、それも同時に破たんした。また、95年3月15日の勉強会の最後に、「まったく経済とは関係ないのだが、近々オウムが何かやります」という話をした。その時のメンバーはオウムという言葉さえ知らなかった。結果は皆さんご存知の通りである。
(パソコン画面を説明して)これは記事のタイトルだけを並べたものなのだが、それまで私はコンピュータというものは使ってなくて苦手だったが、記事が膨大になるので、それを管理するためにやむなくコンピュータを導入して、エクセルを使って、表計算のソフトを表計算に使わずに記事のデータベースとして使うようになった。このように日付順に経済に関する記事の見出しをずっと並べて、色付けした。黄色が通常よりもポイントになりそうな記事。オレンジ系が事件事故。ブルー系が破たん、倒産に関する記事。今回のバブルの発生とその崩壊のもとになったものは何かというと、1985年のプラザ合意から始まっている。1985年までさかのぼって、経済に関する記事の見出しを全部作ってみた。そしてこのように時系列的に並べていくと、日を追うごとにオレンジ系が増え、日を追うごとにブルー系が増えるということが手にとるように分かる。原因なくして何事も突然には起こらない。全部繋がっている、というように見えるようになった。
昨日衆議院選挙が終わったが、自民党の圧倒的多数でこのまま日本の景気が急激に回復するのだろうか? そう思う方、手を挙げて見て下さい。先行きは決して明るくないと思われる方は、それなりの覚悟をしたほうがいいだろう。恐らく早ければ2005年の12月まで、どうにか引っ張ってごまかして、間違って伸びたとしても2010年まで、今の日本の財政は持たない。破たんする。全部数字的に書かれている。国の予算が一般会計で80兆円であるのに対して、国の借金である国債の発行残高が、ここ5、6年で3倍になっている。今年度は450兆円。来年度は500兆円を越える。日本の財政が持つわけがない。日本の財政がクラッシュする最大の原因は、発行している国債の残高がこれだれ増えているのだから、本来、国債の価格は下がるはずなのに、(物が溢れたら物の値段が下がるのは当たり前なのだから)、国債の値段は7月までずっと上がりっ放しだった。国債の値段が上がるということは、今ある利回り・金利が下がるのだ。
だから「20年物国債」の金利が7月の段階で0.46%だった。それが9月段階で1.5%、現在が2%。ということは、たった二か月で国債の金利は4倍になったのだ。つまり国債の価格が4分の1に暴落したのだ。これが何を意味するかと言う事を世の中の人はほとんど理解していない。政治家を含めて。これは始まったばかりだ。これだけ発行残高が増えているのだから、国債の価値が下がって金利が上がるのは当たり前の話だ。それが今まで上がっていなかった。7月に0.5%を切っていたこと事体が国債バブルだったのだ。前回、株式バブルが90年に崩壊し、92年、93年に暴落した。同じように今、国債の暴落が始まった。日本国債の価格が暴落するということは日本の国力が暴落するということだ。ロシアやアルゼンチンと同じようになっても全然おかしくない。なのにほとんどの新聞がそのことを書いていない。あるいは書いてはあっても目立たないように小さくしか書いていない。今の日本経済で一番大きな課題は、国債とその利回りについてだ。本来ならば3%、4%になっても全然おかしくない。
それがそこまでいっていないのはなぜかというと、日銀がジャブジャブの資金供給をして、何がなんでも金利の上昇を押さえているというのが今の状況である。細かく新聞の記事、特に日銀というテーマで読んでいくと、はっきりと手にとるように見えると思う。こういった状況の中で、前述したが、早ければ2005年の12月まで、どう引っ張っても2010年までは持たないだろう。日本の財政がクラッシュする、という前提で皆さんも仕事をしていったほうがいいと思う。今の仕事を続けていて、いずれ景気が回復するだろうとか、何とかなると思ったら大間違いだ。今が最上の状態で、ますますこれから悪くなるというように覚悟しておいたほうがいいと思う。
これは第二次大戦の末期と同じ状況だ。あるいは大戦が終わった状態かもしれない。大戦が終わって助かったのかといえば、そうではない。むしろ終わったあとが大変だった。預金封鎖、新円切り替え、農地開放。全財産、全部取り上げられた。まさにこれからそれが始まるというように覚悟したほうがいいだろう。しかし、そうなってしまった後、日本経済はそこでクラッシュして日本発の世界恐慌になるのか? 日本はこれでおしまいか? というと、そこまで行ったときにはじめて、日本は本来の在り方に立ち返って、急激な発展過程に入ると思う。特に2010年以降は。なぜかと言うと、一つは第二次大戦が終わったときにどうだったか? 大負けして原爆まで落とされて、焼け野原だ。あの時、働き盛りの若い力が三百数十万人殺されたのだ。人もいなかったし金もなかった。それで日本は滅んだか?そこからだ。日本経済が急成長を遂げたのは。一時は米国を抜く所までいった。今回は終戦直後と比べたらどうだろう。インフラはなくなったか?なくなるどころか臨海副都心、六本木、汐留、品川、などが整備されたのはバブル崩壊後だ。
とにかくありとあらゆるインフラが、東京を中心に加速度的に整備されている。整備費用は東京首都圏だけで、バブル崩壊後10数年で30兆円は下らないと思う。東京だけでなく、新幹線は全国に敷かれ、全国に空港が設置され、日本国中ですごいインフラ整備がなされている。インフラだけではない。人が追い詰められて、自殺者が毎年一万人以上。電車がそれで止まるようになっているはいるが、戦時の三百数十万人の比ではない。人がいないわけではない。と同時に、今回はお金がないわけではない。そのお金がどう使われて戻ってくるかどうかは別として、信用創造力の元である個人金融債1400兆円だとか、法人金融債600兆円だとか、為替介入のため米国の国債を買わされたり、ドルを買って持っているだけでも60兆円は持っている。お金はある。それらがまったく正しい方向に使われていないから、日本経済はこのような状態になってしまった。その最大の原因は、全部役人のシステムだ。ある意味で今は官僚の社会主義システムだ。これが諸悪の根源である。これが崩壊する。終戦直後もあの軍部が崩壊したから自由に動けるようになって、急成長できた。
今、すべてを押さえているのは官僚社会主義システムだ。お金がないわけではないといったが、皆さんの中で特別会計という言葉をご存じの方はどのくらいいるか?特別会計のことを本にまで書いて克明に調べたていた人は代議士の石井紘基さんだ。石井氏は2001年までの特別会計の内訳を書いている。その段階で330兆円ぐらい。最新の資料を見たら380兆円だった。一般会計が来年度85兆円なのに対して、特別会計は毎年上がり、今は380兆円。これは国会の審議なくして、役人が自由に使っているお金。これが特別会計。それプラス財投が24兆円。400兆円を四百数十万人の役人が自由に使っている。これが諸悪の根源である。そのことが新聞紙上やテレビでもほとんど言われていない。このことが今の日本の最大の癌である。どこかの段階で必ず表に出てくる。これが表に出された時、まな板の上に乗せられた時、初めて日本の国は変わると思う。これは戦後70年間かけて役人のシステムが癌細胞のように広がった結果である。これについて一切触れられたくないものだから、あらゆる手段を使ってマスコミに載らないようにしているのが現状なのではないか。
そういうことをひとりで取り上げて、二年前に国会でその質問をした結果、石井氏は殺された。そういう状況に今の日本はあるのだと思って頂きたい。そして、明治維新と第二次世界大戦の敗戦と同じ規模どころか、二回の比ではない金額を、すでに日本は失っている。だが前回と違って物はある、人はいるのだから、それをプラスの方向に再改良するために、官僚社会主義システムを一日も早く崩壊させることが必要になって来ている。これが崩壊して終戦後のような自由な形で経済が動き出したとしたら、多分大変な急成長をする。しかも2010年までの段階にだ。
中国は米国と比較して、GDPが例えば、4分の1、5分の1のレベルにまで上がったらどうだろう。人口は12億人。日本の10倍だ。だとしたら、少なくとも米国の3倍のマーケットが、飛行機で渡ったら3時間の所に出現する。今までは中国がデフレの元凶のように言われていた。しかし今の段階で逆転しつつある。中国からの輸入よりも、中国への輸出のほうが金額的にプラスになってきている。2010年までには間違いなく大変な額がプラスになる。米国も完全に日本を抜いて、中国向け貿易額が大きくなった。だからこれから起きることは全部マイナスに取る必要はまったくない。明治維新の時は、それまで体制側だった武士階級が全滅して職を失ったわけだ。だがその時チャンスを掴んだ商人階級の中から三井、住友、三菱が生まれた。第二次世界大戦の敗戦の後は東急、西武が生まれた。同じことが起きる。おそらく100年に一度の大変なチャンスを我々は今、目の前にしていると思う。それをどう自分のものにするかしないかで、はっきり結果的に別れる。
二極化という言葉がよく使われるが、これから起きるというか、すでに起きつつある二極化は勝ち組と負け組の数はフィフティ・フィフティではない。3%〜4%の勝ち組と残り96%〜97%の負け組みだ。中途半端はほとんどない。大事なのは3%〜4%の勝ち組に入るために何が必要かということだ。やはり情報である。自分が情報を捕らえて、その情報を自分がどう生かすかだ。情報というのはただテレビ、雑誌、新聞を見て分かったつもりになっても、そんなものは単なるインフォメーションでしかない。日本語でいうと情報というと一つの言葉だが、英語でいうとインフォメーションの他に、インテリジェンス(知恵)がある。さらに価値のある情報はウィル(意志)がある。自分が知識をまず集めて、その知識をどう組み合わせて新しい知恵を生み出していくか、その知恵を使ってどう生きていくか、どう自分のものにするかによって、残りの人生、残りの会社の運命が決まっていくのではないか。
私はそういうことをやっているうちに、またまた見えてくるものが違ってきて、日本の経済や人のことよりも、自分自身のことが大事だと思うようになった。私の場合は幸か不幸か、記憶力が非常に悪くて、人の顔とか名前を忘れてしまう。人の顔や名前を忘れると、怖いことにその人が持ってきた仕事までも一緒に忘れてしまう。後でエライ目に何度か会い、昔は腰に小さなテープレコーダーをぶら下げて、その情報をパソコンに何時何分に何処で何してどんな話をしたかを全部入れておいた。つまり、パソコンに自分の行為、行動の記録として全部残すようにした。分刻みの毎日のデータがここに入っている。色が変わっていたり印が付いているのは後で見返した時にポイントになる重要な部分である。こういうことをやっていると、驚いたことに、みんな忘れていると思っていた事が、このように文字データでも残しておくと、それを見たとき思い出す。
文字データで思い出せない部分は96年の12月からテープレコーダーをビデオに変えて、ビデオを持ち歩いている。朝起きた瞬間から寝る瞬間まで。朝起きた瞬間は自分の寝ぼけ顔を撮ってどんな夢をみていたのか、が最初。朝の朝刊の見出しとか、朝食に何を食べたかとか、家を出るシーン、会社に着いたシーン、お客さんが来たシーン、お客さんの名刺、全部録画する。1日に30から50項目を撮る。シーンには日にちと時間が入っている。見るとその時のことが全部思い出せる。皆さんもそうだと思うが、例えば小学校三年生ぐらいの遠足の写真が、たまたま押し入れの奥の方から一枚出てきた時、この写真を見た瞬間に例え40年前のものでも、何か思い出すのではないか。本当は人間の脳は全部覚えているのである。しかもこういう過去のデータを見返した時に、その時はそれほど重要だと思わなかったことが、3年経って見返した時に、「アッ、こんなことをこの段階で考えていたのか、今だったら自分だったらこんなことが出来るのではないか、今だったらこういう計画が実現出来るのではないか」ということが沢山出てくる。ある意味で自分の仕事や人生を新たに作り上げていくすべての材料がこのなかにある。
考えてみたら、新聞の記事などは後で取り返しが付く。自分が取り残さなかったとしても、図書館にいけば縮小版もある。自分の行為、行動、思考、感情に関しては、自分が記録を残さなかったら誰も残してくれない訳だ。自分の行為、行動、思考、感情の記録というものは、自分の実体験そのものだ。だとしたら皆さんの仕事における問題点、皆さんの人生における問題点や、これからやるべきこと、その答えは全部過去の体験にあるのではないか。自分でやってみてそれがわかった。それは何でもないような文字の羅列だが、それを見た瞬間から一つのヒントを得て新しい瞬間がどんどん始まる。それこそ、何十億円、何百億円の仕事に繋がる。ビジネスチャンスも、人生そのものを変えるチャンスも、よそにはない。全部皆さんの頭の中にある。それを形に落とし込んで残しておかないと、ただ白紙の紙に向かって何か良いアイデアがないかと鉛筆持って考えてみるだけで、絶対に出て来ないのではないか。
話しはあちこちになるが、これは当社の現在のホームページの表紙だ。ぜひ今日から見てて頂きたい。ホームページの中に私の経済情報が入っている。ここをクリックすると、毎日、新聞社が出している記事データの見出しとリンク先が張り付けてある。見出しを読んでいるだけで、私がどういうものに注目して、どういう記事を選んでいるかということがわかると思うし、記事の内容そのものはリンク先が張り付けてあるので、それをクリックすれば見えるようになっている。ヤフー、朝日、その他、うるさくないところは記事も出している。日経は見出しと言えども出してはいけないというので出していない。色々なところを毎日張り付けているので、無料だから、今日から毎日チェックしてみて頂きたい。皆さんの会社でホームページを実際に立ちあげていらっしゃる方はどのくらいおられるか?。手をあげてみて欲しい。半分ぐらいか。今、手を上げなかった会社は今後、三年以内になくなる。これからは。ホームページなくしてビジネスチャンスはありえないと思う。しかし、いくらホームページを立ち上げても見てもらわなければ意味がない。
どうやって自分が立ち上げたホームページを、自分の会社の存在を見てもらうかが、次の大きなポイントになる。皆さんの会社のホームページで一日アクセスが千件以上ある方はどのくらいおられるか? そのような方はおられないか。昨年の6月の段階で当社のホームページのアクセスは一日5〜600件あった。テレビでもホームページは宣伝している。昔は「よんよんまるまるわんわんわん」の宣伝だったが、4年前に営業権を外資系のリーマン・ブラザーズ社に売ってからウィークリーマンションはやらずに、オフィス系の物件を取り扱うようになった。テレビCMのほか、CMソングを奏でる名刺などを使って、ホームページを宣伝している。あとで名刺交換させて頂くが、この名刺は真ん中のマークを押すと、アドレスの宣伝をするCMソングが流れる。マンスリーマンションなどのサイトだけでも一日5〜600件あったが、あるサイトを加えたら、アクセス件数は一気に10倍になった。何をやったかというと、当社のホームページの中にキャバクラの女の子の顔を出した。今280人ほど載せている。
クリックすると、この子の働いている店の情報とか、プロフィールが出る。そこに当社の商品を張り付けてある。つまりキャバクラの女の子が、ひとりひとり当社の宣伝をしてくれるような形につくった。世の中の男性は本当にスケベだ。これで10倍なのだから。これから先はこんなものではない。携帯電話を使ったデジタル名刺という特許を申請したら、今月特許が取れた。キャバクラに行って名刺を貰っても怖いではないか。家には持って帰れないし、誰が誰だかわからなくなってしまうし。そこで、携帯電話に、顔写真付きの女の子の名刺を貰えるように作ったのだ。これで、おそらく当社のアクセス数は百万件を越えるだろう。それだけのアクセスが取れればテレビのCMをやらなくても良くなるかも知れない。ある意味でホームページは自分で自分だけの放送局を持つのと同じ。膨大な放送局をこれから皆さんで作れる。ただそこで勝負を決めるのは、見てもらえる面白いコンテンツをどういうふうに入れるかということだろう。昔バブルの最盛期に自分の将来の夢として、人工衛星を持ちたいと言っていた。人工衛星は結局持てなかったが、持つ必要はなくなってしまったわけだ。
動画でも何でも、好きな事を流せるようになったのだから。このような時代に入ってきたということを一つ認識して頂きたい。
こういうことをやっているうちにまた自分の興味の対象が段々変わってきて、今度は一挙に死後の世界に行った。まず何で自分がこんな目に会わなければいけないのか、というところから自問自答した。だって私の友達も不動産屋の社長なのだが、バブル最盛期には物凄い生活をしていた。ヘリコプターはみんな持っていた。2年で償却できるとか言って。乗りもしないのに。2年で償却できても乗らなかったら仕方ないのだが。クルーザーというとモーターボートのような物を想像するかもしれないが、汽船のようなクルーザーを乗り回していた。あちこちにゴルフ場を作って銀行員や役人を招待して捕まったが、そういう人が捕まっても仕方ないと思う。しかし、私など軽自動車をずっと乗り回していた。ひたすらお金を借りて土地を買ってウィークリーマンションを建てて、あまりお金が無い人を対象に便利なシステムを作り上げた。なのに不動産業であるという一面だけをとって、どういう生活をしていたとか、社長はどういうことを考えていたのかは一切関係なく、全部一所にひっくり返した。なぜ自分がそんな目に会わなければいけないのか、自問自答した。
そうこうしているうちに、何のための人生なのか?、このまま終わってしまったら、自分の人生は何だったのか?、死んでしまったらどうなってしまうのか?、ということを考えた。(近藤氏に質問して)あなたは何歳ですか? そうですか、53歳ですか。53年前に自然発生したということなのですか? そうではない。つまりお父さん、お母さんがいたから生まれた訳だ。そのお父さん、お母さんもお祖父さん、お祖母さんがいたから生まれた。さかのぼったら生命の誕生は三十八億年前でしょ。だから皆さんの本当の年は三十八億歳なのだ。自然発生したわけはない。クローンで生まれた人でも、もとはあるわけだから。それがひとつ。もう一つは、ご自身の細胞の数はいくつあるか数えたことはあるか? もとはといえば、お母さんの卵細胞にお父さんの精子の細胞がドッキングして、そこから細胞分裂が始まる。1個の細胞が2個になり、それが4個になり、8個になり、3000グラムの赤ちゃんが生まれてくる時にはこの細胞が3兆個に増える。で、60キロの人間だったら、60兆個の細胞で出来ている。そして、60兆個の細胞の中に60兆個のDNAを持っているのだ。こんなことは自然の法則からいってほとんどありえないことだ。
これだけの膨大な数の細胞の中に、これだけの膨大な数のDNAが入っている。そのDNAの一個一個は、スイッチをオンにしたりにオフにしたりして、その人の性格などの情報を組み込んでいる。これは自然の法則からは、確率的に有り得ない程の事だ。三十八億年前に生命が誕生した時、無機質からたった一個の有機質の単細胞の生命が発生した時、その確率は、例えば宝くじに何回当たる確率と同じ確率だとお思いになるか。答えは二百万回だ。たった一個の単細胞でさえそうなのだ。それが人間は三兆個の細胞で作られており、その細胞の一個一個が、この細胞が左手の指先の爪になるとか、この細胞は脳細胞になるとか、全部決められて人間の格好をして生まれてくるなどというのは、自然環境下では絶対にありえないことだ。でも現実にあるからこそ、皆さんが存在している。
我々が作るもの全ては目的を持って作っている訳である。マイクはマイクとして、お皿はお皿として、紙は紙として目的を持って作られている。それにはそれぞれ設計図というものがある。設計図があるからものが出来る。設計図とは何かというと情報である。もっと別のことを言えば、作った人の意思である。作った人の意思が設計図として存在する。それでパソコンも携帯電話も皆使えるようになった。世の中に存在する最高の設計図は何かというと先程述べた人間のDNAである。この設計図に共通することは、作った人の意思の表れだということ。つまり目的を持たされて、すべてのものが作られている。だとしたら究極の設計図であるDNA遺伝子によって作られている我々が、目的を持たずして生まれてきたわけがない。皆さん一人一人が何らかの目的を持って、この地球上に時を同じくして存在している。というように思えば大丈夫だ。全て偶然ではない。全て必然なのだ。
世の中には、何でそんな事が起きるのかということが、奇跡も含めて色々存在する。ニッチもサッチもいかない状態に追い込まれて、一千万円の手形がどうしても落とせない、銀行に行って話をしたが、断られた。もう駄目だなと思って道を歩いていた時に後ろから肩を叩かれて、「元気がなくてどうしたの?」と言われて、振り向いたら親しくしている友人だった。こういう訳で駄目なんだと話すと、「貸してやるよ」と言われて救われるとか。皆さんだってそう言った経験は一回や二回はあると思う。これは超奇現象という。夜中の三時ごろ目が覚めて、なぜ自分はこんな時にトイレでもないのに目が覚めたのかと思っているうちに、また寝てしまったら、翌日電話で、ちょうどその時間に親類が亡くなっていたとか。なぜ、そういうことが起こるのか。それはもう、神のしわざというしか言いようがない。神という言葉は一般的には拒絶反応を与えるが。
なぜ自分がこんな目に遭わなければいけなかったのか、ということも含めて考えると量子力学の世界にたどり着いた。
世の中全て必然。皆さんが今まで生きてきた結果作り上げた世界が、たまたま重なって、こうして一緒にいられる。私が作り上げた、私が思って行動し作り上げた結果としての世界に生きているのだ。皆さんは今の自分が幸せで楽しくて仕方ない、という生活をなさっている方はどのくらいおるか?おられない。今の生活は不満で不安で仕方ないという方ばかりなのか、こちらは。それも誰の責任でもない。今までに皆さんはそういうふうに考え、そういう風に行動してきた結果、そういうふうになったのだから。量子力学の究極の法則は二つある。ひとつは不確定性原理。もうひとつは、電子は粒であると同時に波であるということ。これには光も含まれる。光は光子だが。性格として粒であり波である電子は輪ゴムのような格好をしていて高速に振動している。そして三つのクオークが集まって陽子と中性子を構成し、それが集まって原子核をつくり、その回りに電子が飛び回って原子を構成している。電子が粒で波であるということは、電子は独自の波動数を持っている。
中性子は中性子で独自の振動数を持つから、原子は原子独自の、その原子で出来た物質は物質独自の振動数を持つ。それで作られている皆さんは、皆さん独自の振動数を出しているのではないか。皆さん自身の振動数=波動は強烈で持続性のあるものならば、必ずそれに共振する人が集まってくる。だから皆さんが社員に対し、「あいつは働く気が無くて気に入らない。」「自分の仕事に協力してくれない」とボヤいてもどうしようもない。それは皆さんが呼び寄せているからなのだ。だから自分の必要なものやなりたい自分、道具を含めて、状況を含めて、相手を含めて、みんな自分が呼び寄せているのではないか。そうして出来たのが皆さんのポジションだと思う。
もうひとつは不確定性原理。量子の世界までいくと、物質の究極の存在というものは確定していない。あくまで可能性でしかない。原子の状態でさえ確定していない。すべての物質の行き着くところは不確定なのだ。その状況を確定するのは、観測者の意思なのだ。分かりやすくいうと、機械にコインの表裏をずっと出させると、百回、千回とやっていると大体イーブンになる。ところが人間が、表が出ろ表が出ろと念じて、機械と同じ回数をやると表の回数が増える。というようなことを含めて、不確定性原理という。原子、もしくはクオークのレベルの最小単位までいったら、その方向を確定するのは本人の意思なのだ。自分で自分の状態を作っているのだ。だから世の中にはうまくいく奴とうまくいかない奴の二種類しかない。
エネルギー不変の法則や質量不変の法則というものがある。そういうふうに考えていくと、人間の存在とは何かというと、肉体としての物質、つまり質量と精神という名のエネルギーの複合体ではないかと思う。だから人間の質量が50キロ、60キロあったとしたら、その中に秘めている可能性、エネルギーの大きさはほぼ無限大のものを人間は持っているのではないか。色々な言い方がある。「求めよ、さらば与えられん」とか「成せばなる何事も」とか色々な国の色々な方が色々なことを言っているが、言い方が違うだけで言っていることは同じではないか。そういったことを量子力学的に考えていくと、人間はほぼ無限大に近い精神エネルギーを持たされて、何かの目的を持って世の中に現われるものだ、と思うようになった。だからうまくいく人達に共通して言えることがある。何だと思うか。世の中には、そのことばかり考えている人達がいる。お金持ちになりたい人たち、金儲けしたい人たちは、金儲けのことばっかり考えているから、結果、大金持ちになっているのではないか。人格とか人間性とかはまったく関係ない。へたに人格とか人間性とか云々とかいう奴は全然金儲けは駄目だ。
めったやたらに女性にモテる男性がいる。そういう奴に限って家柄が良くて、学歴があって、背が高くてなどという男性はめったにいない。大抵違う。そういう奴に限って凄い女を連れて歩いている。なぜかというとそのことばかり考えて生きているからではないか。人間性とかそういうものは別にして。そういうものに費やす精神エネルギーが高ければ高いほど具現化してしまう。
先程述べた通り、私はものすごく記憶力が悪いと思っていたのに、自系列的に並べると全部覚えている、ということに気が付いた。そのくらい人間の脳は凄いものだ。人間にはスプーンを曲げるとか、見えなくしたものを透視するとか、密室の中から出てくるとか色々な超能力があるが、たとえスプーンが曲がろうが、人の考えが多少読めようが、その人間は幸せだろうか。そうではないのではないか。もっとも優れた超能力は本当は誰でも持っている。最高の超能力は何だと思うか?それは無から有を生み出すことだ。つまり量子力学的に言ったらば、エネルギーを物体化、実体化する力だ。世の中に存在するものは、エネルギーと物質と時間と空間だけで、それの基本は不確定要素で、最終的には本人の意思が確定する。だとしたら、どういう状況が自分にとって一番都合の良い状況なのか?自分が何百億、何千億の大金持ちの社長になった時のイメージを明確にもって、それを実現するために何を出来るか考えて、出来ることの可能性を全部書き出して、出来ることを一つずつやっていったら、必ずそうなる。私は実体験している。私は普通の人が考えられないようなことを何度もバブル崩壊後に経験している。
普通は、バブル崩壊前に有限会社で一千億くらい銀行から借金していて、バブル崩壊後に貸した本人(担当者)がいなくなって、突然、掌(てのひら)を返したように、貸した金を返せ、さあ金返せ、さあどんどん金返せと言われたら会社はみんなつぶれる。ところが当社は、一昨年の利益が130億円、今期の利益が90億円だ。売上などそんなにないのに。なぜならば銀行が償却費をチャラにしてくれたから。考えられるか?13年前は全く新規の仕事は全く出来なかったのに、13年ぶりに今年、兜町と日本橋に、大型ビルを2棟建てた。現地を見にいって使いたい方があったら、一日や二日は無料で提供するから、どうぞいつでも使って下さって結構だ。兜町のビルは証券取引所のすぐ横、日本橋のビルは日本橋三越から歩いていけるところ。そんなところはバブル時代、坪5千万円から6千万円したところ。どんなに人気の商品で、金を借りられても、商売は絶対に出来なかった。バブルの頃にそんなことをやったら変わり者だ。今だからできるのだ。そういう風に、「なる」と思っていたら、本当に「なる」のだ。13年目の賭けだから。私にとって本年が新たなスタートの年になる。
アラジンの不思議なランプという話がある。あれはランプを擦る事で、アラジンの不思議なランプの大魔王はご主人様の言うとおり、何でも実現してくれる。欲しいと思ったものは全部手に入れられると思っている。人間の脳もどう擦るかによるのではないか。欲しい物が手に入ってないということは、そのランプ、つまり脳をを正しい方向に擦らないで、だめな方向に擦っているのではないか。人間の脳は二つある。左脳は論理的に物事を考える脳。右脳はイメージを司る、どちらかというと芸術的な脳だ。誰だって10億円あったら嬉しい、と思う。嬉しいと思う反面それを手に入れるのは無理だ、と考えてしまう。この辺から皆さん方が日本の教育から受けた偏差値教育の弊害が出てくる。10億円があったら嬉しいと右脳でイメージしても、手に入れるのは無理だとすぐ左脳で否定しまう。ある人の今の年収が1千万円だとする。どう切り詰めて貯金したとしても年にせいぜい100万円、10年経って1千万円、100年経って1億円、10億円貯めるのに1000年かかると、左脳で論理的に考えるから駄目だと思ってしまう。駄目だと思った瞬間から潜在意識が働く。潜在意識が駄目だと思ったことを、そのままものの見事に実現してくれるから、絶対10億円は手に入らない。そうではなく、取り敢えず10億円あったら嬉しいと右脳で思ってみることだ。その夢をどんどん膨らますのだ。10億円あったら今の家を引っ越して、田園調布に住もう。田園調布も昔は30億円ぐらい出さないと豪邸は買えなかったが、今だったら5〜6億円で2〜300坪位買えるなとか、250坪の土地だったらせいぜい家は50坪でいいなとか、明確なイメージをつくることだ。明確なイメージが出来上がるにつれ、本当にそれが何となく出来そうな気持ちになる。出来そうな気持ちになった時、とりあえず何をやるかを考える。銀行強盗をやっても最近はなかなか捕まらない。検挙率は20%を切っているから10回のうちに2回は捕まるが、8回は成功するのではないかとか、可能性のあることを何でも考えることだ。そうこうしているうち、もしかしたらこれは出来るかもしれないという気持ちになる。
私は実現したのだ。私はかつて町の不動産屋だった。事務員が二人しかいなかった。ウィークリーマンションは、やろうと思って始めたのではない。木造のボロアパートばかり管理していたのが、どんどん老朽化し、建て替えも出来ないから苦肉の策として、何か新しい事業を始められないかと思って始めたのがウィークリーマンションだ。やってみるうちに色々トラブルが発生して、それをひとつひとつ解決していくうちに、考えられるすべての犯罪に巻き込まれた。最近は渋谷の小学生4人の事件もあったが、あのビルも当社が管理しているものだが、そういうものも含めて。そのときの「失敗」や「挫折(そんなことはいいたくはないが)」という言葉が、今となって振り返ってみると違う言葉に変わった、何かというと「体験」、「キャリア」、「ノウハウ」という言葉だ。バブル崩壊で一斉に色々壊した。壊しただけですまず、それから13年で立ち直った。ゼロから始めた町の不動産屋がたった7年間で1000億円を借りられる実績を作った。一方それをマイナスにしてしまった実績も持っている。それを13年間何とかやりとげて、ここまで来て、新たな物件を作った体験をもっている。そこで培ったノウハウや
知名度を、また何かをつくりだす力に使ったら、障害になるものは何があるのか。
おわりに桃太郎の話をする。桃太郎はイヌとサルとキジを連れて鬼退治に行く。イヌとサルとキジは何を象徴しているか。イヌは信頼、サルは知恵、キジは勇気を象徴している。つまり家を出て世間の荒波の中に出ていく若者にとって、大切なのは知恵と勇気と信頼なのだというたとえ話である。だが一人で三つとも持っている若者はまずいない。だからそれを持っている仲間を作りなさい、というたとえ話だ。イヌとサルとキジが桃太郎からもらったキビ団子は、毎日の生活のなかで何を意味するのか。さっき述べたが、無から有を生み出すということだ。情報、自分の考え方、発想、これが頭の中だけでは単なる情報で実体化していない。推進している脳のエネルギーを実体化する最初の行動は言葉だ。言葉に出した瞬間にこれは音波として実存性が出てくる。強烈な音はガラスを割ってしまうのだから。それが言葉だ。相手に喜んでもらえるような良い言葉を出せば、それは喜んでもらえることになる。口に出す言葉というものは自分の思いである考え方や自分の概念を最初に物体化することだ。本当に気を付けて出さないと、自分の人生を壊すのは簡単だ。町中で、人の前で変なことを言ったら、それでその人との関係は
終りだ。お客さんを無くしてしまう。虐げるような言葉は奥さんにもお客にも友達にも社員にも絶対に言ってはいけない。気が付かないと思っても、褒めることだ。言葉はたとえば社長が社員を怒鳴ったりして、その社員がそれを苦に自殺しても不思議ではない。そのぐらいの力は持っている
さてキビで作った団子だからは本当はあまり美味しくない。鬼退治に付いて行くということは命懸けで戦争に行くことだから、普通はキビ団子ぐらいではなかなか行かない。しかし日本の昔ばなしを読むとイヌとサルとキジは桃太郎についていった。なぜか。つまり何かに動かされてついていった。何かと言えば信念、使命感というもの。桃太郎は自分が鬼退治に行くために、強烈な信念、使命感のもとに行った。よほどの信念がないと、背中に「日本一」の旗を立てて町を歩けない。皆さん旗を立てて仕事をしているか? 今の経済は戦国時代だ。戦国時代を舞台としたNHKの大河ドラマを見ると、合戦の時、家康や信長の掲げる「天下を取るのだ」という旗印に家来はついていった。こういう戦乱、混乱の世の中で生きるためには自分が強烈な信念、使命感を持つこと、それを示すための旗印を高く掲げることが大事である。ということで、この話を終わりたい。
最後に一つ、今から5年後、私はテレビ、ラジオ、新聞などのマスコミに引っ張りだこになっていると予言する。そうなることを本人が信じている。そうなって当たり前だと思っているから。そして、万が一そうならなかったら、またこちらの講演会に呼んでいただきたい。なぜそうならなかったかを説明させていただくから。
参考:日本鍍金新報
>>戻る
2月例会「欧州めっき企業の生き残り戦略と現状」
昨年、独国のめっき業を見学できる機会に恵まれた。独国の環境規制、ISOの取り組み、空洞化などについて感じたことを話したい。
ドイツケルンのA社は1960年設立。年間売上は何と約140億円。社員205人。工場に携わる人が180人。技術開発スタッフが25人。この人数で140億円の売上は驚異的だ。めっき加工の他にめっき薬品の販売もかなりの比率で行う。めっき薬品(無電解めっき関係)を年間で4500トンから7000トンを販売している。また設備も作って売っている。産学官の連携による実績も多々あり、そこにかかる開発費を国から上手に受け取り、事業を拡大している。商品別の売上げは自動車部品で40%、電子部品で40%、建築関連が20%。新商品(めっき皮膜)開発にも力を入れている。製品は大物から小物まで様々なものがある。大物でも小物でもマスキングを要するものがほとんどで、例えば私の会社では全面にめっきを付けたほうが安い、と顧客に話す程マスキングは手間もかかり、コスト高になるケースが多いが、同社はマスキングが当たり前という感覚が強い。シリコンゴムなどを成型してマスキングの部材として使うなどマスキングは工夫がなされていた。。一部手塗りのマスキングもあった。汎用で使えるように工夫した治具もかなり多く見られた。
工場内は人が目立たない。1ラインに2人ぐらいだ。たまたま見た時には小さなワッシャーのような品物を女性が一人で掛けていて、どれくらい1時間で掛けるのか聞くと、約八千個から一万個くらいとの返事が返ってきた。引っ掛けも工夫されている。テーブル上に大きな枠を固定し、そこに小枝が沢山飛び出ている治具を置き、女性が品物を両手に持ちながら掛けている。こうしたやり方は確かに早いし、効率的だ。引っ掛けられた枠の治具がそのまま、レールでめっきの前処理のスタート部(ロード部)まで動かせるという工夫もあった。どの工場でもそうだが、土地があるから工場はビルではなく平屋だ。天井は極めて高く、ガラス張りだ。消費電力の節約のため太陽光をうまく取り入れている。ガス発生などの事故が起きた時には、ガラス張りがパッと開き排気する。
ベルリンではめっき会社、薬品専業会社等、次の4社を訪問。大手電気メーカのB社は広大な敷地で、町的なイメージ。どこを見ても、レンガ色の大学のような建物が見渡す限り建っている。日本でいう日立市のようだ。ここも一つの部門として表面処理の部門が存在している。年間10億円の売上。表面処理部門に携わっている社員は60人。24時間の3直体制をとっている。主に高電圧電源用接点の部品をめっきしていた。次はC社。年間売上15億円。社員数90人。ほとんどリール・トゥ・リール。3次元のフープめっきに特色がある。3次元の部分めっきとは平面化でなく立体化した部分の一部分だけめっきを付ける技術。通常の2次元フープめっきと比べ、材料費を40%節約出来る。設計段階で、メーカーの開発担当が部品を複雑な形状にしても、必要な所に必要なだけめっきできる。先進的なことを色々考える社長の会社だ。大手電機、自動車メーカーとの取引が多い。D社は年間売上46億円。従業員数300人。めっき加工の他に樹脂の成型、金型製作などを行う。若い社長で、携帯電話関連の部品を主に加工している。バレルや静止のラインが並び、我々の工場に極めて似ており、身近に感じた。
同社で忙しかったのは携帯電話の基地局に使われる部品。自社で成型した特殊なエンジニアリングプラスチックにめっきする。普通のABS樹脂向け前処理ではめっきは付かないという。その次はE社。日本にも支社がある。会社規模は大きく、社員数2300人。これは各国の会社の合計だろう。欧州に35%、米国に25%のシェアを持っている。建物も立派で、研究開発に相応しい色々な設備、機器がずらっと並ぶ。社員はカジュアルな服装で、フレックスタイム制を導入していて、金曜日などは3時をまわると、ほとんど人が会社にはいなかった。次がH社。ここも貴金属のめっき薬品の販売が主。その薬品を使ってファスナー、メガネフレーム、電子部品などの量産試作を兼ねた自動めっきラインを保有している。あらゆる貴金属の研究開発、生産、販売を行っている。見学した時ほとんど人の姿が見られなかった。敷地が広いせいもあるが、人と人がお尻をぶつけ合いながらめっきをしているような状況は一切見られなかった。うまく広い敷地を利用して効率的にあるラインに対して一人ないし二人というような作業者を配置し、一か所で集中したコントロールルームで液管理などを行い、液を日々チェックしている。
次に旧東ドイツエリアの工場は、技術レベルの高いところとそうでないところの差が激しい。ドイツの賃金は大卒で30〜40万円、一般の労働者は22〜26万円程。ドイツには今でもマイスター制度があり、13歳頃からマイスターに進むのか大学(6年制である)に行くのかを選択する。だが、今ではマイスター制度もアメリカナイズされて崩れつつあるという。今回訪問しためっき事業所では、ライン担当者のうち一人がマイスターの資格を持ち、残る人は持っていなかった。
EUの定義によると「すべての残留物が再利用廃棄物と投棄すべき廃棄物のいずれかに分類され、さらに最終的な廃棄物をゼロにしなくてはならない。それが技術的、あるいは経済的に不可能であれば、排出量を出来る限り削減するか再利用しなければならない。それも不可能な場合には、再利用技術が開発されるまで貯蔵すべき」としている。表面処理業界ではEUのELV指令(廃自動車指令)が2006年7月1日、WEEE指令(電気電子部品リサイクル指令)が2005年8月13日、RoHS指令(有害物質使用制限指令)が2006年7月1日に発効される見込みだが、色々な資料によると、この時期も早まる傾向にあるようだ。制限物質は水銀、鉛、6価クロム、カドミウムなどだが、除外項目として高融点はんだの鉛などがある。3価クロムめっきの話は今回出なかったが、亜鉛めっきの6価クロメート処理の代替として3価クロメートや亜鉛−ニッケルめっきを研究しているという話は出た。見た感じ、欧州の企業が同指令や規則に対し、それ程緊迫感を持った感じは受けなかった。私の想像として、輸入物には厳しく、国産の物には甘くしているのか。あるいはもう既に確立した技術はあるけれども隠している
のだろうか・・・。
ドイツでも賃金の安価な東欧諸国に仕事が流れている。特にポーランドは日本における中国的な位置付けにあるという。これはめっき企業に限ったことではなく、ドイツの製造業者が年間3万5千社も倒産していると現地の社長が述べていた。ポーランドの賃金はドイツに比べて6分の1程度。ドイツではまず東欧、次に中国というように仕事が流れていっている。
欧州の自動車業界ではISO9000の方を採用していると聞いている。もともと英国がISO発祥の地であり、EU統合に向けて各国の規格統一の際にISO規格が取り入れられた。よって、EU諸国がISOの最初の導入国とされている。現在ISO9000を一番多く取得している国は英国で、5万件が取得。その次がドイツの1万件、アメリカが1万弱という。今回視察した工場はほとんどがISOを取得しているが、質問して初めて取得していることがわかったくらいで、日本のように看板や名刺に取得を書いてある企業はなかった。つまり、「あって当たり前」ということであろう。品質管理でも環境管理でも、ドイツではISOの取り組みより以前からの実績がある。例えば駅でもごみ箱は金属、燃える、燃えないというように分別されている。そうした取り組みの結果がISOの取得につながっているのだろう。当社でもISO9000シリーズを取得したが、今はまだ手順書通りに物が動かないから是正書を書け、とかで社内が書類の山となっている。確かに勿論、良い点はあるのだが、作業者はかなり大変で混乱していると思う。当社ではISOは順調に機能しているとは言い難い。
今回見た欧州の企業がどうか判らないが、前述のようにベースが最初にあり、その上にISOという認定がついてきたということであれば、ごく自然にISOシステムが運用されて、今後開発の成果などに結びつくのではないか。
ドイツのめっき企業の今後の動向に関して、ほとんど私の感想となるが、ドイツではめっき技術の開発に関して、高品質を維持しつつ、工程数を削減しコスト競争力を向上する方向に進んでいる。特殊技術を備えた皮膜形成技術の重要性が増大している一方、昔からある装飾用、防錆用めっき技術もなおざりにしてはならないという考えも持ち、その辺の技術を他に転換していかなければいけないという危機感も感じているようだ。先ほど紹介しためっき企業の半分は「めっき屋」という認識は無い。めっき加工もしながら、薬品や設備も生産している企業が圧倒的に多く、めっき加工だけの会社は今回視察した中には無かった。だからかなり立場的に強い。メーカーと開発設計段階から情報交換して高品質を確立している。日本のように、メーカーから一方的に品物を渡されるのとは全然違う。
参考:日本鍍金新報
>>戻る
|